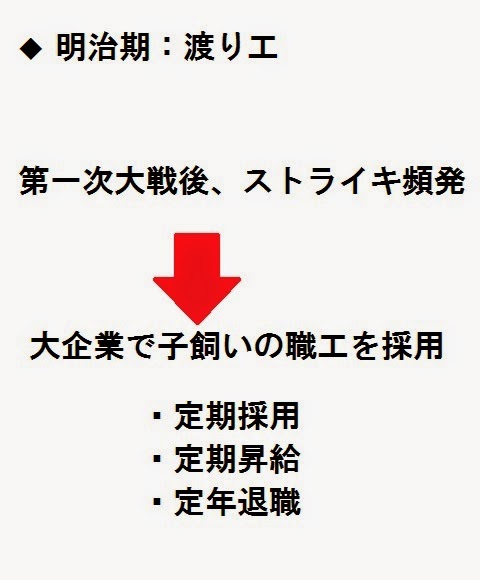ということで、ようやくノートにまとめ終わったので、この本の中身を書いていこうと思う。
世界史、なかでも近代から現代にいたる税制をまとめた本で、終盤では未来に向けての話も載っている。
今回はその中の序盤、絶対王政~市民革命期のイギリス編となる。
◆絶対王政下、戦費の増大と議会発言権の増大
当時、三十年戦争を通じて軍艦建造技術の進歩をはじめとして戦争技術が著しく進展し、そのために戦争遂行の費用が飛躍的に増大した。
絶対王政下といえども、平時はともかく、戦時は臨時税に頼るしかなく、そのためには議会の同意が必要であった。
1625年、チャールズ1世即位。
議会では対スペイン戦の経費をを賄う特別税が14万ポンドしか承認されず、しかも通常、即位した王の生涯承認されるはずのトン税・ポンド税が1年間しか承認されなかった。
王はこれに怒って議会を解散し、承認なしにトン税・ポンド税を徴収する。さらに強制借り上げ金や船舶税の導入など、市民の経済的負担を増やしていった。
1628年、ふたたび議会を招集すると議会は権利請願を起草し、提出する。
「第1項 議会の同意なき課税の禁止」
チャールズはやむなく裁可するが、不満なので翌年にはまた議会を解散する。
以後11年間親政を敷く。その間、税や罰金を増額、新設していく。
1640年、スコットランドとの主教戦争の経費のため、また議会を招集する。
ここで議会は課税の廃止、禁止条項を増やすことを意見した。
◆議会派VS王党派→クロムウェル護国卿政権
国家財政が逼迫して臨時税に頼る度合いが高まるほど、議会の発言力が増していった。
その中で、議会はどんどん過激化し、議会派(過激派)と王党派(穏健派)に分裂する。
1642年10月、両軍が衝突するも、議会派は劣勢であった。
これは、議会軍は軍事調達のための財政基盤がないことに起因した。
そこで1643年、資金調達委員会を設立。
査定課税 Assessd Tax という、財産への直接課税を導入した。
これは一定の財源調達額を各地域に割り振り、財産の査定額に応じた課税を各戸に課すものであったその後、週割査定税、月割査定税として定着し、後のイギリス所得税の前駆となった。
この査定課税は公平課税ではなく、ロンドン市に負担が集中したことが問題であった。
そこで、間接税として内国消費税 Exercise Duty が導入された。
これは生活必需品への課税が強く、庶民も税負担を負うことになった。
当初は戦費調達のための臨時課税のはずだったが、現実には内乱終結後の共和国の窮乏を救うため、課税対象を拡大しつつ恒久化された。
こうして、すでに導入されていた関税に加え、査定課税、内国消費税といった新税の導入が長期的にイギリス財政の基盤を確立することになった。
その後、1645年2月、議会によってニューモデル条例が可決された。
これにより議会軍の再編強化が図られ、総司令官フェアファクス、副司令官クロムウェルの体制が敷かれる。
1646年6月、国王軍が降伏し第1次内乱が終結する。
47年には国王を捕虜とし、48年に第2次内乱終結。
49年1月、チャールズ1世を国家反逆罪で処刑する。
その後独立派と平等派の争いが表面化し、クロムウェル護国卿政権として軍事独裁政権が誕生する。
◆王政復古と宗教対立、名誉革命
60年、チャールズ2世により王政復古が図られる。
この際、課税は議会承認を必須とすること、消費税の一部とポンド税、トン税、関税は国王に供与することが決められた。
1685年、ジェームズ2世が即位し、カトリック寛容政策を敷き、国教会を奉じる議会と対立した。
王が反乱鎮圧を口実に2万を常備軍化。
1687年、88年に王が信仰自由宣言をする(国内は反カトリック)。
1688年11月、オレンジ公ウィリアム3世が軍を率いて上陸すると国王はフランス逃亡。
1689年2月、ウィリアム3世とメアリが権利宣言に署名し、共同王位につく。
これが名誉革命となる。
-----------------------
◆家産国家から租税国家へ
シュンペーターの『租税国家の危機』に曰く、
家産国家 : 国家が保有する財産で国家財政を賄える
租税国家 : 国家の保有財産だけでは支出を賄えず、主として租税財源に依存する
という区分があり、
17~19世紀にかけて、多くの欧州国で家産国家から租税国家への移行が生じた。
これは、絶対王政下で軍事費の膨張と官僚機構の維持のために莫大な費用がかかり、
これは王室財産では賄えず、租税に頼ることになったためだ。
が、租税とは個人財産への介入なので、議会の承認が必要だった。
シュンペーター『租税国家の危機』は、神聖ローマ帝国のオーストリアを事例に、近世領邦国家の領国経営をつぶさに見ていく。
-----------------------
この後、この『私たちはなぜ税金を納めるのか』は19世紀ドイツ、19~20世紀アメリカでの税制の移行や思想についてみていき、
第5章で現在の世界経済について、そして第6章で今後の税制について語る。
現代においても僕たちは税金を納めるわけだが、これは「お上に納める」との考えもあれば「公共サービスを金で買っている」という考えもある。
どちらが正しいとかいうよりは、税制の変遷につれて人びとの意識がどう変わっていったのかを知ることで、いまの自分の考えを形成するための助けになるのではないかと思う。